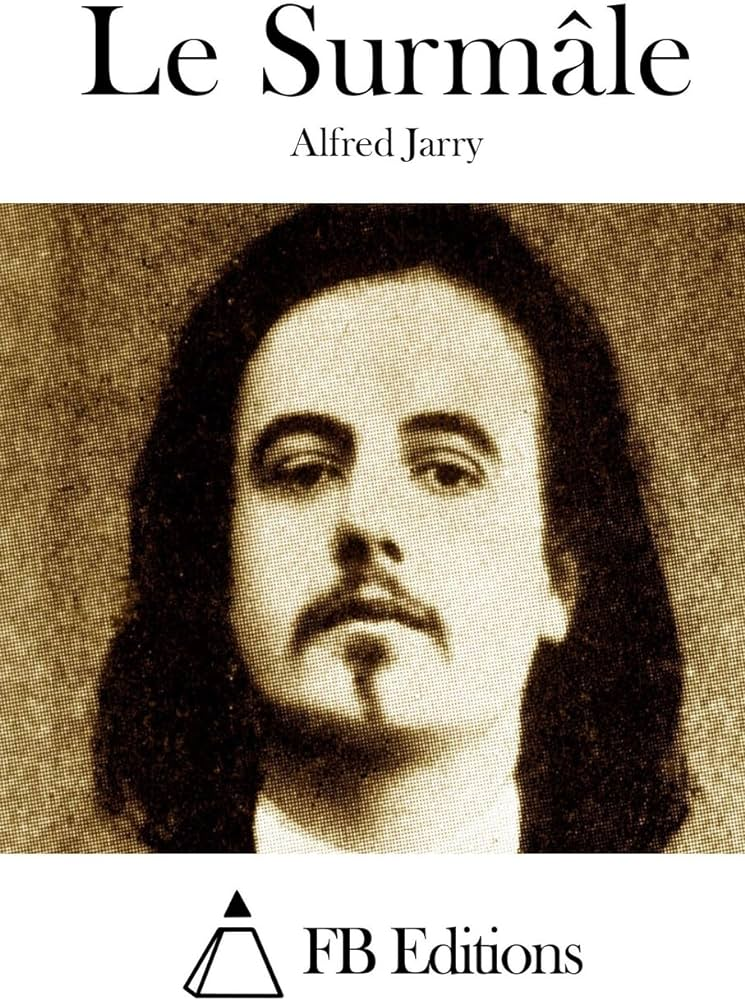
前回の記事で触れたように、アルフレッド・ジャリの「超男性」を読んだ。
ここで取り上げるような作品は100年前のものばかりで、男性中心的な世界の記述がでてきてしまうかもしれない。
超男性
超男性の中に出てくるエピソードは、荒唐無稽だ。
- 無限運動食というのを食べながら蒸気機関車よりも速く(時速300km)、何日も休みなくタンデム自転車を漕ぎ続ける男たち(しかも1人は途中で死に、死んでからも生きていた時より力強く漕ぎ続ける)
- 24時間の性交回数世界一を目指すチャレンジ
- 電気椅子にかけられたが、なぜか電気椅子よりも高い電圧で電気椅子側に電気を流し始める人間
といったものが描かれる。
「超男性」の中ではスポーツもセックスもどちらも目的は同じで、男性の力強さを定量的に計測するための手段でしかない。
「超男性」の最後の方には
金属と機械が全能になった現代では、人間は生きのびるために、機械よりも強くならなければならない、昔、人間が獣よりも強かったように・・・それは単なる環境への適応だ・・・この男は未来の最初の人間なのだろう・・・
というメッセージが現れる。
スポーツもセックスも、超男性が獣よりも機械よりも強いことを示すためのテストでしかない。そこには努力や愛といった美徳が排除されている。
「超男性」においては特にスポーツの方は、人間対人間の競技ではなく人間と機械の対決になっている。スポーツの歴史にはあまり詳しくないが、タイムを競ったりする競技って比較的新しいものなんじゃないだろうか。 相手(人間)との相互行為だと思われていたそれらを、相手を不要(または誰でも良い)ものとして捉えるようになったとき、人は独身者と呼ばれる、、のかもしれない。
力の表象
かつてはライオンとか熊とか人間より強い獣が力の象徴だった。非実在のものも含めれば、龍だとか双頭の鷲だったりもある。 人間よりも大きかったり力強いだとか、そもそも人間にできないことー空を飛ぶとか火を吐くとかーもできる。
しかしその後、燃料で動く金属製の機械がさらなる力強さ・速さ・能力を見せるようになる。 獣よりも機械の方がより力を表すのに相応しい。
マリネッティの未来派宣言が「速度」を賛美するのも、そこに人類が過去に見たことがないような力強さが感じられたからではないだろうか。
We declare that the splendor of the world has been enriched by a new beauty: the beauty of speed. A racing automobile with its bonnet adorned with great tubes like serpents with explosive breath ... a roaring motor car which seems to run on machine-gun fire, is more beautiful than the Victory of Samothrace.
現代における力の表象
昔に比べると身の回りにある機械も油で動く巨大な無骨な鉄の塊ではなく、微弱な電気で駆動する、プラスチックを使った温かみのある?小さなものが増えた。 鉄道も自動車も無骨な塊という感じはなく、有機的な曲線があしらわれるようになりTHE鉄の塊感は無くなってきている。
実際にはエンジンやモーターの力強さは上がっているはずなのに、現代の機械は力の表象としてのインパクトは弱くなっているように思う。 そんな今、力を表象するものはなんなのだろうか? 現代にジャリが生きていたとしたら、「人間は生きのびるために、●●よりも強くならなければならない、昔、人間が獣や機械よりも強かったように・・・」の●●に何を入れるか。
ソフトウェアやアルゴリズムといった目に見えないものが力を持つにつれて、形のある力の表象というのが無くなってきていて思い付かない。 より高速な計算機が今の力の表象になるのだろうか?でも絵でより早いCPUを描くのってどうするんだろう。
余談:機械の時代と全体主義
「赤旗の歌」のようなやたらと威勢のいい革命の歌も、個人の趣味嗜好ではなく革命のために身を捧げようというのも一種の自分を巨大な機械の一部と同化させたいという欲望に由来するものではないだろうか。
キリスト教の神が生きる指針を与え、そのために生きていればよかった時代は終わったけれども、じゃあ何のために生きているのか?がわからない。 その問いに悩む「独身者」の心の空白を埋めるために「ゲルマン民族のため」「共産主義革命のため」etcという物語が多数編み出されて、その目的のためにより多くの戦果を産んだものが英雄とされる。 与えられた目的のため、より多く・速く与えられた役割を果たす。そんな機械が男性の目指す道であるという時代意識が、「凡庸な悪」を生み出す一つの土壌であったのではないか。
